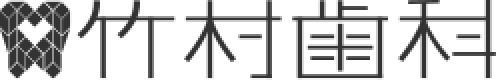誤嚥性肺炎を防ぎましょう
みなさん、こんにちは!
竹村歯科本町医院です。
2025年問題の一つに後期高齢者急増があります。
実際、誤嚥性肺炎でお亡くなりになられる方も増えてきています。
今回は、「誤嚥性肺炎」について説明させていただこうと思います。
よろしくおねがいいたします。
竹村歯科では、訪問診療もさせていただいております。
よかったら、ご利用くださいね 🙂
誤嚥性肺炎とは何か
誤嚥性肺炎は、本来であれば食道を通って胃に向かうはずの食べ物や飲み物、または口腔内の細菌を含んだ唾液などが、誤って気管や肺に入り込むことによって引き起こされる肺炎です。
健康な人であれば、嚥下反射や咳反射によって異物の侵入を防ぐことができますが、加齢や疾患によってこれらの機能が低下すると、誤嚥のリスクが高まります。
特に注意が必要なのは、高齢者、脳血管疾患の既往がある方、認知症の方、神経筋疾患を患っている方などです。
これらの方々は嚥下機能の低下により、日常的に誤嚥のリスクにさらされています。
また、意識レベルの低下や薬剤の影響により、正常な嚥下機能が阻害されることもあります。
誤嚥を起こしやすい状況と要因
誤嚥が発生しやすい状況を理解することは、効果的な予防策を講じる上で不可欠です。
まず、食事中の姿勢が重要な要因となります。背筋が伸びておらず、前かがみになったり、横になったままの状態で食事をすることは、誤嚥のリスクを大幅に高めます。
また、急いで食べることや、一度に大量の食べ物を口に入れることも危険です。
食べ物の性状も重要な要因です。
液体は最も誤嚥しやすく、特に水やお茶などのサラサラした飲み物は気管に入りやすい特徴があります。
一方で、パンやクッキーなどの乾燥した食品も、口の中でバラバラになりやすく、誤嚥の原因となることがあります。
さらに、口腔内の状態も誤嚥に大きく影響します。
口腔内が乾燥していると、食べ物がうまく飲み込めず、残留物が気管に入る可能性が高くなります。
歯の状態が悪く、十分に咀嚼できない場合も同様のリスクがあります。
食事時の基本的なケア方法
誤嚥性肺炎を予防するための最も基本的で重要なケアは、適切な食事環境の整備です。
まず、食事時の姿勢を正しく保つことが不可欠です。椅子に深く腰かけ、足裏全体を床につけ、背筋を伸ばした状態を維持します。
ベッド上で食事をする場合は、上体を60度以上起こし、膝を軽く曲げた安定した姿勢を取ることが重要です。
食事のペースも重要な要素です。
ゆっくりと時間をかけて食べることで、嚥下反射を適切に働かせることができます。
一口の量は小さめにし、十分に咀嚼してから飲み込むよう心がけます。
また、食事中は会話を控えめにし、食べることに集中することも大切です。
食べ物の温度にも注意が必要です。
熱すぎるものは口腔内を火傷する可能性があり、冷たすぎるものは嚥下反射を鈍らせる可能性があります。
人肌程度の適温で提供することが理想的です。
【監修】院長 元島慧
○院長経歴
2012年 朝日大学歯学部卒業
2016年 大阪市内にて勤務
2020年 本町医院 竹村歯科院長就任
○参加セミナー
2016年 大阪SJCDエンドコース (根管治療)修了
2017年 明海・朝日臨床審美コース (審美治療)修了
2017年 i6 Implant Education 第一期 (インプラント)修了
2017年 大阪SJCDベーシックコース (総合治療)修了
2017年 山田國晶先生エンドベーシックコース (根管治療)修了
2017年 山田國晶先生主催CERIclub(総合治療)参加
2018年 大阪SJCDマイクロエンドコース (根管治療)修了
2018年 牛窪先生Bio Raceを極める!ベーシックコース(根管治療)修了
2018年 ADPR定位置埋入コース (インプラント)修了
2018年 ストローマンベーシックインプラントロジー1Dayコース (インプラント)修了
2018年 第6期GPOレギュラーコース (矯正治療)修了
2018年 大森塾7期 (総合治療)修了
2019年 大阪SJCDレギュラーコース (総合治療)修了
2019年 山田國晶先生エンドレベルアップコース (根管治療)修了
2021年 CREDセミナー (保存治療)修了
2022年 臨床歯科麻酔管理指導医取得
2022年 日本顎咬合学会認定医取得
所属学会
日本臨床歯科学会
日本顎咬合学会 認定医
日本顕微鏡歯科学会
臨床歯科麻酔管理指導医