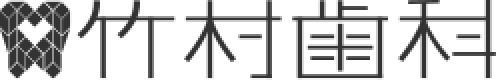フッ素と食べ物の関係について理解しよう
こんにちは🎵
本町医院 竹村歯科です。
今日は「フッ素と食べ物の関係」についてお話しします。
フッ素はむし歯予防に大きな役割を果たす成分ですが、
実は日々の食生活とも深い関わりがあります。
食べ物をうまく活用することで、むし歯予防効果をさらに高めることができるのです。
今回は、フッ素の基本的な働きやどのような食品に多く含まれているのか、
さらに食事の工夫でむし歯を防ぐポイントについて詳しく解説していきます。
言うまでもなく歯科医院での定期検診に勝るものはないですが、
参考程度にご覧いただければと思います。
⸻
1. フッ素の役割とは?
フッ素は歯の表面にあるエナメル質を強化し、
むし歯菌が作り出す酸による溶解(脱灰)を防ぐ働きがあります。
また、すでに始まっている初期のむし歯の再石灰化(修復)を促進する役割も果たします。
具体的な作用は以下の3つです:
① エナメル質の強化
エナメル質は歯の表面を覆っている非常に硬い層ですが、
食事や飲み物による酸の影響を受けると溶けやすくなります。
フッ素はこのエナメル質に結合することで,
フルオロアパタイトというより硬く、酸に強い構造を作り出します。
この結果、酸による脱灰(溶解)を防ぎ、むし歯の発生リスクを軽減します。
② 再石灰化の促進
食事の後、口の中は酸性に傾き、エナメル質からカルシウムやリンが溶け出していきます。
これが脱灰と呼ばれる現象です。
しかし、フッ素が存在すると、唾液中のカルシウムやリンがエナメル質に再吸収され、
再び硬い層が形成される「再石灰化」が促進されます。
この修復作用により、初期のむし歯は自然治癒することもあるのです。
③ むし歯菌の抑制
むし歯の原因菌であるミュータンス菌などは、食べ物の糖を代謝して酸を生み出します。
この酸が歯を溶かし、むし歯が進行します。
フッ素には、この菌の活動を抑える働きがあり、酸の産生を減少させます。
つまり、フッ素があることで菌の力を弱め、むし歯の進行を抑えることができるのです。
⸻
2. フッ素を含む食べ物
フッ素は自然界にも存在し、私たちが日常的に摂取する食べ物や飲み物にも含まれています。
特に以下の食品に多く含まれています:
食品 フッ素含有量の目安(mg/100g)
緑茶 0.3〜0.5 mg
海産物(魚介類) 0.2〜0.4 mg
肉類 0.1〜0.2 mg
穀類(米、麦など) 0.1〜0.2 mg
果物・野菜 0.02〜0.1 mg
① 緑茶
緑茶は特にフッ素を豊富に含んでいる飲み物です。
お茶の葉自体がフッ素を多く含むため、
特に深蒸し茶や粉末茶を摂ることで効率よく取り込めます。
食後にお茶を飲む習慣はむし歯予防に効果的です。
さらに、緑茶にはカテキンという殺菌成分も含まれているため、
口内の細菌を抑制する効果も期待できます。
② 海産物
魚介類や海藻にもフッ素が含まれています。
特にイワシやサバなどの小魚を骨ごと食べることで、
より多くのフッ素を摂取できます。
魚の骨にはフッ素が蓄積されているため、
シシャモやワカサギのような丸ごと食べられる魚はむし歯予防に効果的です。
③ 肉類・穀類
鶏肉や牛肉、豚肉にも微量ながらフッ素が含まれています。
また、米や麦などの穀類にも存在しています。
特に玄米や全粒麦は栄養価も高く、フッ素を摂取するには最適な食品です。
④ 野菜・果物
野菜や果物にもフッ素は含まれますが、その量は少なめです。
ただし、野菜や果物をよく噛んで食べることで唾液が増え、
口の中の自浄作用が高まり、むし歯のリスクが減少します。
これはどんな食べ物にも言えることですね。
⸻
3. 食事の工夫でフッ素を活かす
フッ素の効果を最大限に活かすためには、食事のタイミングや摂り方も重要です。
① 食後の緑茶でリスク軽減
食後に緑茶を飲むことで、口内の酸性化を抑え、むし歯のリスクを減らします。
特に温かいお茶は唾液の分泌も促進するため、口内環境の改善にもつながります。
② 骨ごと食べられる魚
カルシウムと一緒に摂ることでフッ素の再石灰化効果が高まります。
シシャモやワカサギなど骨ごと食べられる魚はおすすめです。
カルシウムは歯の成分でもあるため、フッ素との相乗効果でエナメル質がさらに強化されます。
③ 野菜の摂取で唾液の分泌促進
噛み応えのある野菜を食べることで唾液の分泌が促進され、
フッ素がより広がりやすくなります。
生野菜やリンゴなどを積極的に取り入れましょう。
⸻
4. フッ素の摂りすぎに注意
フッ素は健康に良い影響を与えますが、
過剰摂取はフッ素症(歯の白斑やエナメル質の変色)を引き起こす可能性があります。
特に小さなお子様の場合、フッ素の適量管理が重要です。
日常の食事からのフッ素摂取は基本的に問題ありませんが、
フッ素サプリやフッ素入りの歯磨き粉を併用する際は注意が必要です。
⸻
5. まとめ
フッ素は食べ物からも日常的に摂取できる大切な成分です。
特に緑茶や海産物などに多く含まれているため、
普段の食事に取り入れるだけで自然とむし歯予防につながります。
食後の一杯のお茶や小魚を骨ごと食べるなど、簡単な工夫で歯の健康を守ることができます。
また、過剰摂取にならないようバランスも大切です。
適切なフッ素の利用と日々の正しい歯磨き、定期的な歯科検診を心がけることで、
長く健康な歯を維持することができます。
いずれにしても定期検診にはしっかりと通いましょう⭐︎
【監修】院長 元島慧
○院長経歴
2012年 朝日大学歯学部卒業
2016年 大阪市内にて勤務
2020年 本町医院 竹村歯科院長就任
○参加セミナー
2016年 大阪SJCDエンドコース (根管治療)修了
2017年 明海・朝日臨床審美コース (審美治療)修了
2017年 i6 Implant Education 第一期 (インプラント)修了
2017年 大阪SJCDベーシックコース (総合治療)修了
2017年 山田國晶先生エンドベーシックコース (根管治療)修了
2017年 山田國晶先生主催CERIclub(総合治療)参加
2018年 大阪SJCDマイクロエンドコース (根管治療)修了
2018年 牛窪先生Bio Raceを極める!ベーシックコース(根管治療)修了
2018年 ADPR定位置埋入コース (インプラント)修了
2018年 ストローマンベーシックインプラントロジー1Dayコース (インプラント)修了
2018年 第6期GPOレギュラーコース (矯正治療)修了
2018年 大森塾7期 (総合治療)修了
2019年 大阪SJCDレギュラーコース (総合治療)修了
2019年 山田國晶先生エンドレベルアップコース (根管治療)修了
2021年 CREDセミナー (保存治療)修了
2022年 臨床歯科麻酔管理指導医取得
2022年 日本顎咬合学会認定医取得
所属学会
日本臨床歯科学会
日本顎咬合学会 認定医
日本顕微鏡歯科学会
臨床歯科麻酔管理指導医