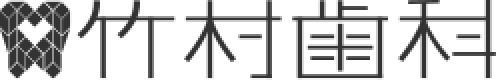唾液について①
- 2025年4月2日
- その他
みなさん、こんにちは!
竹村歯科 本町医院です。
4月になり、桜も咲き始めてきましたね 🙂
満開な桜も散りゆく桜もどちらも同じくらいきれいですよね 🙂
さて、今回は「唾液」について説明させていただこうと思います。
よろしくおねがいします!
唾液は、私たちの日常生活において重要な役割を果たす体液の一つです。
食事中や会話中に自然と分泌される唾液は、消化の補助だけでなく、口腔内の健康維持にも欠かせません。
その役割は多岐にわたり、全身の健康とも密接に関わっています。
順番にみていきましょう!
唾液の成分と特徴
1、主な成分
唾液は約99%が水分で構成されていますが、その他にもさまざまな成分が含まれています。
酵素(アミラーゼなど):デンプンを分解し、消化を助ける。
電解質(ナトリウム、カリウムなど):pHバランスを調整する。
抗菌成分(リゾチーム、ラクトフェリンなど):細菌の増殖を抑える。
ムチン:粘性を持ち、食物をまとめやすくする。
2、pHの特性
唾液のpHは中性に近く、口腔内の酸性環境を中和する役割があります。
これにより、虫歯や歯周病のリスクを軽減します。
唾液の主な役割
1、消化の補助
唾液に含まれるアミラーゼは、食物中のデンプンを分解して糖分に変える役割を果たします。
また、ムチンが食物を滑らかにし、飲み込みやすくします。
2、口腔内の清潔維持
唾液は、口腔内の細菌や食べ物のカスを洗い流す働きを持っています。
これにより、口臭の予防や虫歯のリスクを軽減します。
3、歯の保護
唾液は、エナメル質の再石灰化を促進し、歯を酸から保護します。
また、抗菌成分が虫歯や歯周病を引き起こす菌の増殖を抑えます。
4、発声の補助
唾液は口腔内を潤滑に保つことで、滑らかな発音を助けます。
唾液が不足すると、口腔内が乾燥し、発声が困難になる場合があります。
唾液分泌の調節因子
1、自律神経の影響
唾液の分泌は主に自律神経によって制御されています。
副交感神経が活発になると唾液の分泌が促進され、緊張状態では分泌が減少します。
2、食事の影響
酸味の強い食品や香りの良い食べ物は唾液の分泌を刺激します。
これは、食物を効率的に消化するための自然な反応です。
3、加齢による変化
加齢に伴い、唾液腺の機能が低下することがあります。
これにより、ドライマウス(口腔乾燥症)を引き起こす可能性があります。
唾液不足が引き起こす問題
1、口腔内の疾患リスク
唾液が不足することで、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
また、口腔内の細菌バランスが崩れることで、口内炎などの炎症が起こりやすくなります。
2、ドライマウスの症状
口腔内の乾燥感
口臭の悪化
飲み込みや発声の困難
今回は、ここまでにしますね 🙂
次回は、唾液についてパート2という形で、「唾液量を増加させる方法」や「唾液の歴史」、「唾液検査」等々について説明しようかと思います。
【監修】院長 元島慧
○院長経歴
2012年 朝日大学歯学部卒業
2016年 大阪市内にて勤務
2020年 本町医院 竹村歯科院長就任
○参加セミナー
2016年 大阪SJCDエンドコース (根管治療)修了
2017年 明海・朝日臨床審美コース (審美治療)修了
2017年 i6 Implant Education 第一期 (インプラント)修了
2017年 大阪SJCDベーシックコース (総合治療)修了
2017年 山田國晶先生エンドベーシックコース (根管治療)修了
2017年 山田國晶先生主催CERIclub(総合治療)参加
2018年 大阪SJCDマイクロエンドコース (根管治療)修了
2018年 牛窪先生Bio Raceを極める!ベーシックコース(根管治療)修了
2018年 ADPR定位置埋入コース (インプラント)修了
2018年 ストローマンベーシックインプラントロジー1Dayコース (インプラント)修了
2018年 第6期GPOレギュラーコース (矯正治療)修了
2018年 大森塾7期 (総合治療)修了
2019年 大阪SJCDレギュラーコース (総合治療)修了
2019年 山田國晶先生エンドレベルアップコース (根管治療)修了
2021年 CREDセミナー (保存治療)修了
2022年 臨床歯科麻酔管理指導医取得
2022年 日本顎咬合学会認定医取得
所属学会
日本臨床歯科学会
日本顎咬合学会 認定医
日本顕微鏡歯科学会
臨床歯科麻酔管理指導医